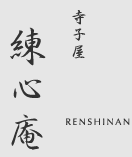2015/11/20 11月期 初歩からの宗教学講座
11月20日に行われた「初歩からの宗教学講座」のリポートです。
記:多谷ピノ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回の「初歩からの宗教学講座」は「映画の中の死者儀礼-東アジア編-」と題されまして、伊丹十三監督の『お葬式』、中国映画の『涙女』、韓国映画の『祝祭』、台湾映画の『父の初七日』の宗教儀礼のシーンを視聴しました。
釈先生がおっしゃるには、今の日本は葬儀の変容時期だそうです。
確かに、「終活」を始め、葬儀への関わり方は私が子供の頃と比べても大きく変わってきていることを実感します。
直葬、家族葬、自然葬……いろいろな形態のお葬式が新たに提案されております。葬儀を始めとする「儀礼」とは一体なんなのでしょうか。そんな疑問を抱いて講座に聞き入りました。
==============
「儀礼」がもたらすもの
==============
まず儀礼には、「社会的コミュニケーション」と「象徴的コミュニケーション」があるそうです。社会的コミュニケーションとは、「こんにちは。何処へ行くのですか?」「ちょっとそこまで」という会話のような、一見意味のないものがそれにあたるそうです。
それに対しての「象徴的コミュニケーション」は、なんらかの象徴やシンボルをつかって「見えない世界」を表現することだそうです。宗教儀礼はこちらに分類されるとのことでした。
儀礼に理屈はあまり必要なく、「その場に身を置く」ことが重要だとのことでした。儀礼なしに一年過ごすのは人間としてきつい、という先生の言葉に深く納得しました。
毎日同じような日常を送っている私たちですが、やはり「儀礼があるからリセットされる」ものがあるわけです。だからこそ新しいことにも踏み出せるのでしょう。
毎日がお祭りのような現代社会はいわば、ずっと「ハレの状態」です。刺激が強く、煽られてばかりの状態では、リセットされる実感がなく、日常と非日常の落差が感じられないに違いありません。
「儀礼」によって社会は区切りをつけているのだと、あらためて納得しました。
==============
「強化儀礼」と「通過儀礼」
==============
さて、「象徴的コミュニケーション」に含まれる宗教儀礼ですが、さらに大きく「強化儀礼」と「通過儀礼」の2つに分けられます。
強化儀礼とは「日常を生きる力を活性化させる儀礼」です。お祭りや法要などがそれにあたります。「非日常状態」、いわゆる「ハレ」で、日常を再点検するのです。
もうひとつの「通過儀礼」は、「カテゴリーからカテゴリーに移動する儀礼」です。家から家へと移る結婚式、子供の領域から大人の領域へと移る成人式。そして、「生」から「死」へ移るお葬式。
死というものを超える「通過儀礼」が葬儀だと先生はおっしゃいました。「死を超える」。すごい言葉です。葬儀を通して私たちは「死を超える物語を共有」し、そののちも、「死者とともに生きる」のです。
「死者の視線を気にして生きること、死者の言葉に耳を傾けることは、きっと人類を鍛錬してきた」と先生は続けて説明してくださいました。人類の知性や情性がそうやって鍛錬してきたのだとの言葉に、連綿と続くひとつの流れをはっきりと感じました。
「なぜ人間は死者儀礼を営むのか」の問の答えが「人間だから」としか言い様がないとのことが、心に染み入りました。
==============
「定型」の持つ力
==============
伊丹十三監督の『お葬式』の表現方法で、先生は「限定コード」と「精密コード」のコミュニケーション理論について説明してくださいました。限定コードとは、決まりきった言い方で、精密コードとは自らの言葉で語るものだと。
限定コードのほうがレベルが低いと思われがちです。実際、コミュニケーション理論ではそのようです。ですが、「儀礼」に関しては限定コードのほうが力を持つことを、先生は宗教者として体感されているそうです。
葬儀の場で、なんの言葉も届かないほど悲しみにうちひしがれているご遺族に、決まりきった言い方をすることで事態がちょっとずつ動くのを何度もご覧になってきたそうです。「定型」だからこそ、相手も安心するのでしょう。様式の持った言葉の方が力を持っている」と先生はおっしゃいます。伊丹監督の『お葬式』はまさにその限定コードと精密コードが交互に出てくるのだと。
そういった視点で映画を見れば、それぞれの儀礼に目がいきます。文化や歴史、様式は違っても、宗教儀礼の持つ力は変わらないのだろうと思いました。
==============
日本仏教と葬儀
==============
俗に日本では「亡くなったら仏になる」と言います。ですがそれは「仏教ではありえない」ことだそうです。それよりも、「結び目が解ける=ほとけ」の説が日本ではしっくりくるのではないかとも。なにか大きなところに戻っていくのが「ほとけ」なら、「死んでブッダになる」よりもわかるとのことです。
本来の仏教からはありえないけれど、「死んだらほとけ」というストーリーは日本における死の文化を支えているそうです。日本人は仏教を受け入れたのと同時に、死に関して真面目に考え始めました。それまでの日本人にとって、死は「できるだけ遠ざけるもの」でしたが、「人間はそうやって死ぬ」という仏教が入ってきたおかげで受け入れるようになったとのことです。
理屈ではない宗教性と直結されるのが儀礼であり、儀礼そのものに力があるのだとすれば、それらを感じるアンテナを日々磨いていきたいと思いました。
現代日本では「自分の死んだあと人に迷惑をかけないように」という思いから終活をされている方が多い気がします。けれどそこにもうひとつ、儀礼の持つ力を共有していることを加味したら、「通過」するにあたっての考えがまた変わるのではないかと思いました。